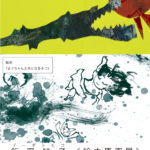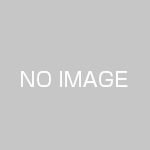<ヤナの思い出と墨で絵を描いた切っ掛け>
商店街のアーケードから落ち、頭蓋骨を割る怪我したあとだった。小学六年生の頃だ。
当時、東京の町田、鶴川駅から歩いて30分のアパートに住んでいた。木造の一戸建てや未だ平屋が立ち並び、とにかく、ごちゃっとしていた。
頭蓋骨は割れたままで、人口骨を付ける前だった。頭を保護するために黒いメッシュのヘルメットを被っていた私の姿は異形で、友だちも近づかず、いつも一人だった。
学校から帰る道は、急な坂道だった。赤いランドセルは、私を後ろにひっぱり体をのけぞらせるように歩いていた。坂道を上りきったところに枯れかかった柳があった。黒くごつごつしていて、樹液か雨露がしたたっていた。根が蛇のように絡むちょうど間のところに見知らぬ白黒のブチの子猫がニャーニャー泣いていた。生後3か月ぐらいだろうか、まだ歩もおぼつかない子猫だった。しゃがんでじっとみる私をネコもじっと見つめ返していた。
気付いたら、猫をうちへ持って帰っていた。どうして両親は猫をうちへいれることを許してくれたのかわからないが、布団に入ってからも猫と見つめ合っていた。
柳の下で拾ったからヤナと名付けた。
突然、引っ越しが決まった。子どもにとっては大人のすることはいつも突然だ。ヤナを親戚のおばさんに預け、わたしはニュータウンへ引っ越しが決まった。引っ越しをしてもヤナのことが頭から離れなかった。一人でいることが多く、柳の木があると、木をグルっとまわり、うろの闇をのぞき込み、猫を探したりしていた。雨が降るとトタンに落ちる雨音がニャーニャーと聞こえてしまう。
季節は巡り、春、夏、秋、冬と数か月経ったころだった。
ひんやりとした空気に薄い青い空の中、電車に乗っているとき、ヤナがお別れにきた。
車窓に映し出される青い空に、くっきりと浮かぶヤナの姿が見えた。言葉はなかったが、はっきりと、お別れに来たのだった。全然怖くなく、むしろ嬉しくって、「ヤナ、ありがとう」とつぶやいた。お別れに来た瞬間にヤナが私と一体になったと実感した。
母に、そのことを告げると、何も言わず、口をきりっと横に閉めたのだった。
大人になって聞いたが、おばさんのところにいたヤナは交通事故で死んでいた。
母は何も言わずに、闇を見続けていたわたしを静かに見守っていてくれたことに感謝したい。わたしもそんな母になりたいと思う。
この絵本を上梓しようと思った切っ掛けは、墨で筆をあそばせていたときに、滲みや流れる黒い液体にヤナを思い出したことでした。その話をコーイチに話したところ、すぐに物語を作ってくれて、この絵本ができました。
墨の黒は、ぼんやりとにじむ思考を漆黒の闇へいざない、
ヤナと一体となった体験を想い起こさせました。
作品になったことで、ヤナは今という永遠へ太陽の光よりも眩しく濃く目の前にあらわれてくれました。そんなヤナが子どもたちのまえにもニャーニャーとあらわれてくれたら作者としてこんなに嬉しいことはありません。
この『よっちゃんと木になるネコ』は、そういう絵本です。